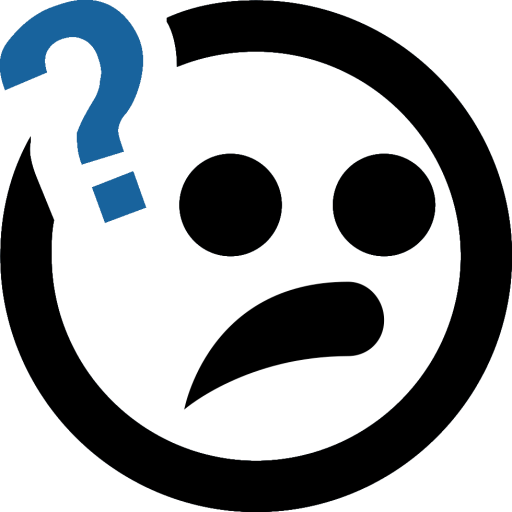労働生産性は企業の重要な指標です。経営課題を解決するメディアプラットフォーム「四国総合研究所(
***
労働生産性は、企業の業務効率を示す重要な指標です。自社の労働生産性と他の企業との比較を知ることは重要です。
そこで今回は労働生産性について徹底解説していきます。
労働生産性とは何ですか?
労働生産性とは、1人当たり、あるいは1時間当たりどれだけの成果を上げているかを示す指標です。
言い換えれば、労働生産性が高いということは、一人当たりの生産高が高いことを意味します。また、「労働生産性が高い」ということは、少ない労力で一定の成果を上げることができると言えます。
そもそも生産性とは何でしょうか?
では、生産性とは正確には何でしょうか?
日本生産性本部 (
何かを生み出すためには、人、金、物、情報などの経営資源が必要です。このように、「何かを生み出す要素」を生産要素といいます。
これらのことから、生産性とは、人、金、物などの資源を効率的に利用することを指します。
労働生産性の計算方法
労働生産性の計算方法には、物理的労働生産性と付加価値労働生産性の 2 つの方法があります。
物質的な労働生産性という観点から見ると
肉体労働生産性とは、生産される製品の大きさ、重さ、数量などの物理量を単位とした生産性を指します。
製品の価格は社会情勢などにより変動しますが、生産現場の純粋な生産効率を測定する場合には、物理量を単位とすることがより効果的です。
したがって、計算式は非常に簡単で、一人当たりの肉体労働の生産性を求める場合は、「生産量÷労働者数」となります。
肉体労働の時間当たりの生産性を求める場合は、「生産量÷(労働者数×労働時間)」となります。
付加価値労働生産性の観点から
付加価値労働生産性とは、企業が生み出す新たな価値の単位で測定される生産性です。
計算式は「付加価値÷従業員数」です。
付加価値額とは、売上収益から「原材料費、外注加工費、修理費、電気代等」を差し引いた金額を指します。
また、付加価値は一般的に人件費として労働者に配分されるか、利益として資本に配分されます。当時、付加価値労働生産性も分配率を決める際の重要な指標の一つでした。
労働生産性の判断基準
先ほど紹介した計算方法で自社の労働生産性を計算してみても、良いのか悪いのかは分からないかもしれません。
そこで、ここでは日本の労働生産性の平均値と業種別・国別の比較を紹介します。ぜひ参考にしてください。
日本の労働生産性の推移はどうなっているのでしょうか?
日本生産性本部が発表した「日本の労働生産性動向2022」(
したがって、「4.950円」があなたの会社の労働生産性が高いかどうかの基準となります。
また、4,950円という数字は1995年の調査開始以来最高であり、長期的には徐々に生産性が向上していると考えられる。
時間当たりの実質労働生産性の伸び率は+1.2%で、2年ぶりのプラスとなった。新型コロナウイルスによる出勤制限や営業自主規制の緩和が主な要因とみられる。
労働生産性の国際比較
日本生産性本部の「2022年労働生産性の国際比較」によると、OECDのデータによると、2021年の日本の時間当たり労働生産性は49.9ドルとなる。
これは、労働生産性が 85.00 ドルで OECD 加盟国 38 か国中 27 位である米国の 60% 未満に相当します。
労働生産性は前年比1.5%上昇したものの、これまでの調査では依然として最低ランクにとどまった。
また、日本の一人当たり労働生産性は81,510ドルで、ODEC加盟38カ国中29位でした。
以上の結果から、日本の一人当たり時間当たり労働生産性は先進国の中でも相対的に低いことが分かります。
産業別の労働生産性の比較
中小企業局の2020年版中小企業白書を見ると、建設業、製造業、情報通信業、卸売業の労働生産性が相対的に高いことがわかります。
しかし、これらの産業では企業規模の違いにより労働生産性の変動が大きく、規模間格差も大きい。いずれの場合も、業界の多重下請け構造が顕著であることが要因と考えられる。
また、宿泊業、飲食業、小売業、生活サービス業、エンターテインメント業などは総じて労働生産性が低い。
簡単に言うと、toB業界は労働生産性が高く、toC業界は労働生産性が低いと言えます。
ただし、これはあくまで業界の比較であり、同じ業界であっても企業によって労働生産性は異なることに留意してください。
労働生産性の向上による 5 つのメリット
労働生産性の向上により以下のようなメリットが得られます。
・人材不足の問題は解決される。
・ワークライフバランスの向上が図れる
・トータルコストの削減が可能
・筋肉質な管理構造に変換可能
・政府からの優遇措置が受けられる
それぞれについて説明します。
メリット1:人材不足の解決
労働生産性を高めることができれば、人手不足の問題も解決できるかもしれません。
現在、日本は少子高齢化による労働人口の減少が社会問題となっています。したがって、労働生産性が向上すれば、少ない労働力で生産量を維持することができ、人手不足の問題は解決されます。
人材不足に陥っているのであれば、採用を増やすよりも労働生産性の向上に目を向けたほうが良いでしょう。
メリット2:ワークライフバランスを向上できる
労働生産性を向上させることで、ワークライフバランスを改善することができます。
近年、働き方改革の深化に伴い、労働時間の短縮や雇用形態の多様化が進んでいます。しかし、単に労働時間を減らすだけでは、当然生産量も減ります。
したがって、労働生産性を高めることができれば、生産量を維持しながら労働時間を短縮することも可能となるはずです。
ワークライフバランスの達成が難しい場合は、福利厚生を強化するだけでなく、生産性向上策も導入する必要があります。
メリット3:トータルコストを削減できる
労働生産性の向上によりコストを削減できます。生産量を維持しながら人件費を削減できるからである。
人件費は金銭的な要因だけを指すわけではありません。労働時間や従業員の健康状態も対象となります。
「経費が無駄」と思ったら、労働生産性を計算してみましょう。隠れたコストがあなたの会社を悩ませているかもしれません。
メリット4:無駄のない経営体制に変革できる
労働生産性の向上は、無駄のない経営構造につながります。変化の激しい現代社会では、自由に動く組織が生き残る。
したがって、無駄な資源(脂肪)を削減し、継続的に収益を上げられる事業や将来性のある事業(筋肉)に注力する必要があります。また、経営体制がしっかりしていると株価も高く評価される傾向があります。
経営体質を改善したいなら、労働生産性の向上から始めるのが一番です。
メリット5:政府からの優遇措置が受けられる
労働生産性を向上させると政府から報酬が得られます。その名も「生産性向上特別措置法」。
具体的には以下のような優遇が受けられます。
・固定資産税軽減措置(3年以内に半減ゼロ)
・生産性向上に必要なキャッシュフローをサポート
・一部補助を優先します。
この優遇措置を受けるためには、まず地方公共団体が導入促進基本計画を策定する必要があります。
なお、特典を得るには「先進設備導入計画」の策定と検証が必要となるため、利用時にはスケジュールの調整が必要となります。
上記の条件を満たしていれば、労働生産性を高めるための国の優遇措置を受けることができます。ぜひご検討ください。
労働生産性を向上させる4つの方法
では、労働生産性を高めるためには具体的に何が必要なのでしょうか?
代表的な方法は次の 4 つです。
・投入量の削減(コスト削減)
・出力増加(性能向上)
・インプットとアウトプットの削減(事業撤退)
・インプットとアウトプットの増加(企業投資)
それぞれについて説明します。
方法 1: 投入量を減らす (コストを削減する)
1 つ目の方法は、入力の量を減らすことです。
今回紹介した4つの方法のうち、最短で生産性を高めることができる方法です。コストを削減すればいいだけだからです。
具体的には、無駄な業務の削減やリストラを実施することで、短期的にはコストを削減できます。
しかし、このアプローチは長期的な労働生産性の向上につながらないことが多く、生き残っている従業員や部門にストレスを与える可能性があります。
とはいえ、これは間違いなく実装が最も簡単な方法です。大手テクノロジー企業が2022年末から大規模なリストラを実施したのはこのためかもしれない。
方法 2: 出力を増やす (パフォーマンスの向上)
ここでは生産量を増やす方法をいくつか紹介します。従業員のパフォーマンスを向上させるための措置を開発することで、生産性を向上させます。
具体的な例としては次のようなものがあります。
・業務プロセスの効率化
・ITツールの導入
・人材育成
・人員配置の見直し
・アウトソーシングの活用
「インプットの量を減らす方法」ほどではありませんが、即効性の高い方法と言えるでしょう。
方法3:インプットとアウトプットを減らす(事業を撤退する)
入力を大幅に削減したい場合は、同時に出力も削減する必要がある場合があります。
具体例としては、事業の撤退、不採算部門の売却、人員削減などが挙げられます。
このアプローチを導入するには、大胆な決断が必要です。しかし同時に、生産性を大幅に向上させることもできます。無駄のない経営体質を作るためには、採算の見通しが立たない事業を売却するという考え方もある。
方法4:インプットとアウトプットを増やす(企業投資)
生産量を大幅に増やすには、投入量も増やす必要があります。
具体的には新規事業や事業拡大などが挙げられます。このような場合、従業員のパフォーマンスを向上させるだけでなく、より多くの新しい人材を雇用する必要があるかもしれません。
また、このアプローチは中長期的には大きな成果を生む可能性を秘めていますが、失敗のリスクも高いというデメリットもあります。経営者の判断力とタイミング感覚が問われる取り組みと言えるでしょう。
要約する
この記事を終わりにしましょう。
・労働生産性は、生産量を労働量で割ることで計算できます。
・労働生産性の向上には多くのメリットがある
・労働生産性を高めるには、(1) インプットを減らす、(2) アウトプットを増やす、(3) インプットとアウトプットを減らす、(4) インプットとアウトプットを増やす、の 4 つの方法があります。2つの方法があります
少子高齢化が進む今日の日本社会において、労働生産性を向上させることは非常に重要です。まず、あなたの会社の現在の労働生産性を計算し、労働生産性がどのくらいであるかを決定します。
労働生産性を高める方法はたくさんありますが、少なくともITツールの活用は不可欠です。近年、ChatGPTなどのAIツールが注目を集めています。早期に導入すれば他社との差別化が図れるかもしれません。
【この記事の執筆者】
知学研究所編集部 / 株式会社知学編集部 「『経営』を身近に」をコンセプトに、経営業務に役立つ記事を制作しています 3,000社以上に導入されている科学的手法も公開。
・アドバイザー紹介はこちらから
引用:知月研究所